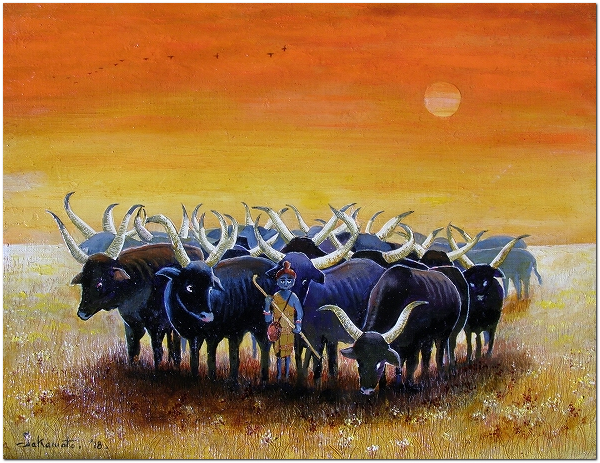今月の初め、土砂降りの雨をついて新宿・若松町の「産業遺産情報センター」を旧友5人で見学した。同センターは2015年に「明治日本の産業革命遺産」がユネスコの世界遺産に登録された際、その内容を広く周知する目的で設立された。
内容は、幕末から明治にかけての50年間に、日本が成し遂げた急速な近代化を産業に焦点を合わせて展示しているものだ。申請に際しては九州・山口を中心に8県11市に分布する23の遺産を取り上げ、いわばこれらが全体として日本の産業近代化をもたらしたという視点から膨大な資料を準備した。イギリスが150年かけて実現した産業革命を、日本は50年という1人の人間の生涯の間に達成したとのこと。ボランティアのガイドさんが力説していた。産業遺産の中心は製鉄・製鋼、造船、石炭産業にかかわるもので、製鉄では官営八幡製鉄所、造船では三菱長崎造船所、石炭では高島・端島炭鉱と三池炭鉱が選ばれている。
この中の端島炭鉱は通称「軍艦島」と呼ばれている三菱の炭鉱であった。今回の見学の主目的は、この端島についてどのような展示がなされているのかを知るためであった。端島は元々小さな岩礁に過ぎなかったところを、三菱が護岸を築き埋め立てを重ねて、南北480m、
東西160m、周囲1,200m、総面積63,000㎡(19,000坪)にまで拡張した。
三菱以前には幾人もの事業家がこの岩礁での石炭採掘に挑んだが、台風襲来の激浪でことごとく失敗していた。明治23年に三菱の経営となり、当時の技術陣は懸命の努力で堅牢な護岸を築くことに成功した。石材を積み上げ天川(石灰と赤土の混合物)を用い、イギリスから輸入したセメントも使ったようだ。埋め立てには石炭採掘で出るボタを利用した。また、この小さな人工島に多くの人たちを住まわせるには、建築物の高層化は必然であり(最盛期には5,000人が住んだ)、最初に建てられた鉄筋コンクリート造7階建て住宅は大正5年に完成した。わが国でその後に建てられた住宅用の鉄筋コンクリート造建物は、10年後の昭和2年の東京・青山アパートであった。住宅以外での鉄筋コンクリート造の建築は大正3年の東京駅と三越本店、大正9年の工業倶楽部等であった。
ちなみにコンクリートには貴重な輸入セメントに、骨材は対岸の野母半島の海浜からの砂と砂利を洗浄して運び、水は天水に加えて製塩の蒸留水を使ったと社史にはある。このようにして洋上に浮かぶ孤島に最新技術を駆使して産業と生活の拠点を作り、日本の発展を支えた先人の功績には存分に敬意を払うべきであろう。
その端島が産業革命遺産に登録されることを知った韓国は、当時官民挙げてその阻止に動いたことは記憶に新しい。軍艦島は朝鮮人が強制連行され強制労働をさせられたところであり認められないという理由である。確かに戦時中、朝鮮から来た人たちが働いていた事実はあるが、それは強制的に連行したものでも強制的に労働させたものでもなく、日本人と全く同じに働いていたと元島民たちが証言している。このいわれなき偏見や誤解に基づく誹謗中傷は、先人に対する冒瀆に他ならない。
その一因を作ったのは、実はNHKの「緑なき島」という昭和30年放送の20分のドキュメンタリーにある。当時三種の神器をいち早く備えた豊かで先進的な端島の生活を紹介した番組なのだが、坑内現場の作業の様子が全くの捏造であることが明らかなのだ。坑口を入る鉱員はきちんと作業着にキャップランプを装着しているのに、坑内現場の作業では褌一丁の裸で四つん這いで仕事をしている。まるで奴隷のような姿だ。これはおそらく、厳しい保安規則でテレビカメラが坑内に入れなかったために、端島とは無関係の筑豊の小ヤマの映像を代わりに使ったのに違いない。韓国は実際にこの映像を強制労働の証拠として映画やキャンペーンに使っている。ところがNHKは国会における厳しい追及にもかかわらず、今に至るも捏造であることを認めていない。後世に生きる我々には先輩たちの名誉を守る責務がある。正しい理解を得るために産業遺産情報センターを訪ねた次第、2時間の見学で大いに勉強した気分になって新宿の街に繰り出し、気勢を上げたことは言うまでもない。
それにしても昭和49年の閉山から50年近くたち、今や長崎観光の目玉になった観のある軍艦島クルーズを見るにつけ、「オレたちは見せもんじゃなかぞ」という元島民たちの呟きが聞こえてきそうな気がする。
(了)
なお産業遺産情報センターは次の通り。
新宿区若松町19-1 総務省別館 0120-973-310(要予約) 土日休館
都営大江戸線「若松河田駅」河田口から徒歩5分 ガイド付きで約2時間コース
|